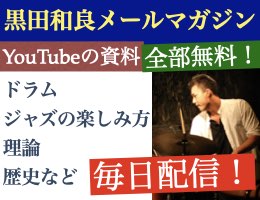ビルはこのトリオを結成するまでに音楽的にこんな構想を考えていた。
「ただひとりの演奏を他の人が追随するような形ではなく、トリオが相互にインプロフィゼーションする方向で育っていけばいいと思う。例えば、もしベース・プレイヤーが自分の演奏で答えたい音を聴いたとする。(注釈:頭の中に聴こえたとする。)それなのにどうして4/4拍子を後ろでただ引き続けている必要があるんだ!」
この当時、こういった演奏するバンドはまだなく、ベース・ドラムはあくまでアドリブのサポートと考えられていた。
今では当たり前にされるこのスタイルも、ビルが完成させたからこそですね。
スコットラファロがスタンゲッツバンドにいた時はあくまでシンプルなライン奏者ですからね!